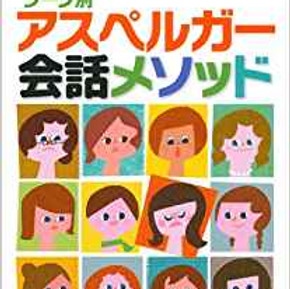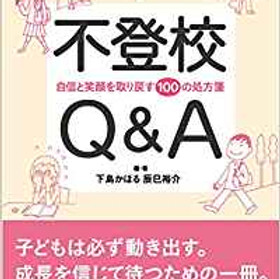お知らせ
外来診療時間
月金(午前のみ)火水土(午前・午後)
午前 10:00~14:00/午後 16:00~20:00
※木曜日は訪問診療のみ
<休診> 日曜日・祝日
※検査についてのご予約は電話でお願いします。
磁気刺激によるうつ病(うつ状態)の治療です。
一度のお試し・相談だけでも大丈夫です。ご興味がある方は電話で相談を受けております。または、問い合わせフォームから、メールアドレスか電話番号、件名に「TMS相談希望」と記入し送信してください。当院から御連絡させて頂きます。
参考図書

医療者/援助者向け
井上令一 (監修), 四宮滋子 (翻訳), 田宮 聡 (翻訳)
メディカルサイエンスインターナショナル
何か1冊国際的な診断基準に則った詳しい本を入手したい方にはおすすめします。翻訳がやや分かりにくいところもありますが、構成自体は日本の教科書より工夫されています。
医療者/援助者向け
大熊 輝雄 (著), 「現代臨床精神医学」第12版改訂委員会 (編纂)
金原出版
辞書的に使うか、詳しい知識を一から学びたい方に向いています。お亡くなりになる前は大熊輝雄先生が一人で執筆されていて、一貫性が特徴でした。まだ、伝統の残っている本です。
医療者/援助者向け
山内 俊雄 (編集), 小島 卓也 (編集), 倉知 正佳 (編集), 鹿島 晴雄 (編集)
医学書院
精神科専門医試験のテキストとしてまとめられた本ですが、精神科医が身につけておくべき最低限の知識を示している点で意味があるように思います。
一般向け、医療者/援助者向け
山下格(やましたいたる)(著)
日本評論社
医師のみでなく援助者に向けて書かれた教科書。通読用の中では、記述も簡潔ながらポイントが押さえられており、おすすめです。
一般向け、医療者/援助者向け
姫井 昭男 (著)
医学書院
薬の本の中では一番のおすすめです。実践的な知識が、かなり踏み込んで書いてあり、治療上の役に立ちます。また、著者の熱意が伝わってきて、印象に残る内容です。
一般向け、医療者/援助者向け
井上 猛 (編集), 桑原 斉 (編集), 酒井 隆 (編集), 鈴木 映二 (編集), 水上 勝義 (編集), 宮田 久嗣 (編集),
星和書店
辞書的に使用する薬の本としてはこちらをおすすめします。いくつかあるこの種の本の中では比較的薄く、記述が分かりやすいです。
医療者/援助者向け
American Psychiatric Association (著)
医学書院
国際的な診断基準の参照用として必要であると思われます。診断基準の要点を簡単に押さえたいときに役に立ちます。
医療者/援助者向け
融 道男 (翻訳), 小見山 実 (翻訳), 大久保 善朗 (翻訳), 中根 允文 (翻訳), 岡崎 祐士 (翻訳)
医学書院
行政関連ではこちらの診断基準を使います。ICD‐11も発表されていますが、まだICD‐10が使用されています。DSMと比較して、記述的で分かりやすい基準が多いです。
医療者/援助者向け
春日 武彦
医学書院
実は一番おすすめしたい本です。援助者としてどのように関わったら良いのか、迷ったときにとても参考になります。是非一読していただきたいと思います。
一般向け
本田秀夫著
一部を抜粋させてください。「……単に既存の情報を整理しただけの啓発書ではありません。『自閉症スペクトラム』について実感を持って深く理解し、生活に活かせる知識と知恵を身につけていただくことをねらいとしています。」例が豊富で目に浮かぶような描写がされています。
医療者/援助者向け
熊倉伸宏著
簡単に言えば、精神療法家の心構えを説く本であると思います。精神療法・心理療法の各方法論について述べた本は多くありますが、このような人と人の出会いとしての「面接」の本質について論じた本は少ないと思います。
一般向け
大野裕著
認知療法の本は非常にたくさんありますが、うつや不安の対処として自分で療法をしたいという人にはこの本をすすめています。認知療法の考えを含めて体系的に学びたいという方には、別の本が向いていると思いますが、とにかく実践したいという方にはとても目的に適った本と言えます。
一般向け
浅岡雅子著
うつ病の治療を中心とした認知行動療法の本は多いですが、パニック・強迫性障害まできちんと視野におさめた本はめずらしいです。PART4の「セルフカウンセリング」が秀逸で、一歩一歩カウンセラーが一緒にすすんでくれるような問いかけがなされています。
一般向け
司馬理英子著
一般的な会話の方法について示された後は、シーン別(会社やママ友、子どもが相手など)でより臨場感を持たせて自習できるように工夫されています。会話の基本をおさえる目的でおすすめできる本です。
一般向け
下島かほる・辰巳裕介:編著
広範な質問に対し、見開き2ページで、一つの回答が完結しており、さらに最後に2~3行でまとめがしてあります。ご家族や本人にとって、不登校対応の手がかりを与えてくれると思います。
一般向け、医療者/援助者向け
上原芳枝著
「どうしたら良いのか」に徹底して応えようという本です。「発達障害」の診断後、どのように生活していったら良いか提案できるように、診断の先を見据えた姿勢を大切にしている内容です。
一般向け、医療者/援助者向け
イルセ・サン著
「なぜこんなに音・におい・相手の表情が“気になってしかたがない”のか?」
生き方のヒントになる考え方の一つに“HSP:Highly Sensitive Person(とても敏感な人)”があります。「鈍感な人たち」や「敏感な自分」とうまく付き合う方法について様々な視点から語られています。
一般向け
森下克也著
通常の西洋薬による薬物療法にも問題点も含めてきちんとふれられており、全体的にバランスよく書かれた「パニック障害」の概説書という印象があります。「薬なし」にこだわった本ではなく、患者さんの利益を重視した治療全体に言及してある内容です。
一般向け、医療者/援助者向け
リー・ベアー著
強迫性障害の治療に関して書かれた本としては定番といえるかもしれません。この分野の第一人者が詳しく症状や治療に関して説明しています。多くの例が理解を促し、物語性をもって記憶に残ります。
一般向け
田村浩二著
強迫性障害は薬も良く効く場合がありますが、最終的にご本人の主体的な取り組みや症状に対する理解が重要な病気と言えます。その取り組みを支える上で、体験に即した強い言葉を集めた本書はおすすめです。
一般向け、医療者/援助者向け
金馬宗昭:著
全体として、深い理解と共感を感じます。
著者自身が青年期から数年間ひきこもりの時期を経験されているということが大きいのかもしれません。助言やはげましが常に「いっしょにやっていこう」という姿勢で発信されています。
一般向け
西井重超:著
精神疾患や症状についての解説本は多いのですが、多くの用語に焦点を当てて、これだけ分かりやすく、印象に残る工夫がなされている記述の本は少ないと思います。
一般向け
マンガ:細川貂々 監修:牧野真理子
「うつ病」のなかまを概観するのにとても役立つ本になっています。題名の通り「いろいろある」うつ病について、簡単過ぎず、長過ぎず、ちょうどいい量の解説と理解を促すマンガが載っています。
一般向け
岩本友規著
前半は障害による度重なる困難を経験した後、どのように発達障害を「克服」したのかが書かれれており、後半に著者の経験をを実践可能なかたちである「生き方」としてまとめたマニュアルが続きます。発達障害は良くなるし、人はずっと発達するという立場から書かれた本です。